ここ数年、自分は1日1食の生活をしています。
で、さらに踏み込んだ「不食」について興味が出てきたので、秋山佳胤(よしたね)さんの『不食という生き方』という本を読んでみました。
この記事では、『不食という生き方』という本の感想、実際に不食はできるのかどうか考えてみたいと思います。
もくじ(各リンクから移動できます)
そもそも不食とは
不食(ふしょく)とは文字通り、「食べないこと」です。
ただ定義が曖昧で、水も食べ物も何もとらない人もいたり、青汁だけを飲む人もいるようです。
不食とは言っても、状況によっては何かを口にすることもあるようなので、「超少食」という言葉が近いのかもしれません。
著者・秋山佳胤とはどんな人か
2008年3月以降、水も食べ物も摂取していない不食の方です。
普段は弁護士として仕事をしながら、健康や不食に関する講演や著作活動もしています。
著者の秋山さんの場合は基本的には水も食べ物も何もとらない人らしいですが、付き合いでたまに食べたりはしているそうです。
栄養を取り入れるためではなく、コミュニケーションツールとして最低限の食事をされているようです。
『不食という生き方』を読んでみて思うこと・感想
不食は我慢ではない
秋山さんは不食を無理にやっているわけではなく、やりたいからやっていると書いています。
ダイエットのためにおこなっているわけではないようです。
ちなみに、断食と不食はどちらも食べないという意味合いのため、同義語のようなイメージがあります。
本書のなかでは、断食は「無理に食欲を抑えつけるやり方」で、不食は「食べなくてもいいという姿勢で、徐々に食べないことに慣れていくもの」という感じのようです。
無理している時点ではそれはもう「不食」ではなく、「断食」ということのようです。
別に食べなくて自然の状態でいられるというのが「不食」という状態なのかもしれません。
不食のコツは食べない生活に体を慣らすこと
最初から完全に食べないことを目標にするのではなく、食べる量を減らした結果、気づいたら食べなくてもいい(不食)という形での達成が理想的だと感じました。
本書では、食べない生活に体を慣らすことがポイントと紹介されています。
現在、僕は1日1食の生活に慣れていますが、この”慣れ”の感覚はよくわかります。
まったく食べないこと(不食)に慣れる、というのはちょっと未知の世界です。
過食は心の飢えが原因
現代の飽食社会で生きる僕たちは、毎日グルメ情報に取り囲まれていて、食の情報が目先をちらつきます。
僕の場合で言うと空腹ではなくてもおいしそうなものがあり、ちょっとしたストレスがたまっている状態であれば、食欲にスイッチが入ってしまいます。
スマホでネットニュースばかりを追っているときは感情が乱れて無駄に間食をしたりしてしまいます……。
日々の生活でたまってしまうストレスを解消するための方法として「食」があります。
やはり、食事は純粋に空腹を満たすためにおこないたいものです。
不食以前に、ストレスを「食」で解消しない姿勢をまずはつくる必要があると感じています。
好きなことをして時間を忘れると不思議なのことに食欲がわいてきません。
何か好きなことをするのがおすすめです。好きなことがなくても、興味があることを調べつづけるという作業をするだけでもOKです。
「時間を忘れるほどに没頭する」が少食生活のキーワードかもしれません。
現在1日1食の人間は、不食という生き方をできるのか
現在、僕は1日1食の生活を続けています。
これはダイエットが目的で始めたわけではありません。
ただ「食べない」ことに体が慣れてしまって、1日1食の生活が基本設定・あたりまえになってしまっているためです。
『不食という生き方』の本のなかで、秋山さんが実際におこなった不食へのステップはこちらです。
1.まずは肉食をやめて乳製品を減らす(徐々にゼロへ)
2.次に主食を玄米菜食へと切り替える
3.それが軌道に乗ったら1日の摂取を野菜と果物だけにする
4.それが軌道に乗ったら果物だけの摂取へと移行する
5.最終ラウンドは1日の摂取をフルーツジュースだけという生活に切り替える
現在、僕は1日1食生活をしていますが、いきなり何も食べないというのは体が慣れないと思うので現実的に不食生活に進むとしたら、とりあえず下記だったらいけそうな気はします。
というふうに、まずは果物(フルーツ)だけを食べる日を取り入れて、体を超少食に体を慣らすことからはじめるのがいいかな、と感じています。
まずはごはん・麺などの主食を食べずにフルーツだけの食生活だったらできるかもしれません。
「食べなくても大丈夫」という考え方を意識の中に徐々に浸透させることが大切かもしれません。
賃金が上がらず、物価ばかりが上がる時代で「不食」は強い
賃金が上がらず、物価が上がる状況で簡単にできる節約方法は「食べないこと」ですね。
この物価上昇と合わせて、異常気象が継続して最終的には地球規模の食糧不足になるでしょう。
そのときに、少ない食べ物を大勢で争って奪い合いになるのは悲しいことです。
そのような争いを回避するためにも、食べないでもOKな人間がこれからどんどん生まれてくる気がします。
食べないで生きていためにも、この『不食という生き方』を読んでおくべきタイミングがきているような気がします。
超少食になるまでには5年以上はかかりますから、今から不食の練習をはじめておくべきかもしれませんね。
でもまあ、まずは1日1食を目指すのが現実的です。
そのときにおすすめの考え方があります。
それは「少食は愛と慈悲の行為」というものです。
断食療法で多くの患者を救った医師・甲田光雄先生の言葉です。
甲田先生は、少食によって動物や植物を殺さずに済むという考えを持っていました。
いまSDGsとかいう言葉が流行していますが、人が食べる量を減らすことこそが、いちばんのSDGsです。
まとめ
世間で食に関して取り上げられるとき、だいたいが超大食いの方についてです。
その逆の超少食(不食)の方についても存在するんだな、と『不食という生き方』を読んで知りました。
超大食いの方が存在するのであれば、超少食の方がいても不思議ではないですよね。
『不食という生き方』を読んだあと、食べない日を意識して作ってみようと試みました。
しかし、生きていくためには「1食は最低でも食べないといけない」という意識が根付いており、夜になると夜ごはんのことが頭に浮かんできて、自動的に何かを食べてしまいました。
なので現在、夜だけは食べる1日1食生活に留まっています。
食事が自動的に頭に思い浮かぶのは、自分がいま没頭できる何かを持ち合わせていないからだな、と感じています。
寝食を忘れて取り組める何かがない(みなさん、ありますか?)。
そして、退屈さが生活のなかで顔を出したとき、ふと「何か食べたいな」となり、余計な間食にも手を出してしまうというパターンが多いです(思い当たる方は多いのではないでしょうか)。
食事はひまつぶしとしての役割も果たしているな、と感じています。
不食をするためには不食に意識を向けるのではなく、人生のなかで時間を忘れるくらいに没頭できる何かを持つ。
それこそが意外に不食への近道なのかもしれません。
不食についてもっとくわしく知りたい人はぜひ、秋山さんの本を読んでみてください。
不食の人の感覚をしれますし、その感覚はこれからの人口増・環境悪化の地球で生きる上で絶対に知っておいたほうがいい内容です!

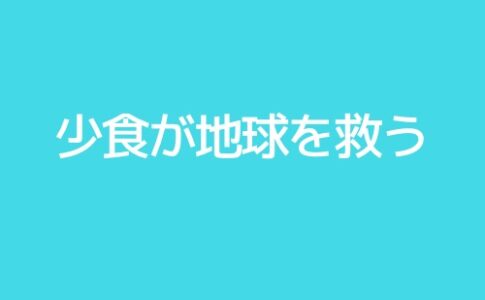
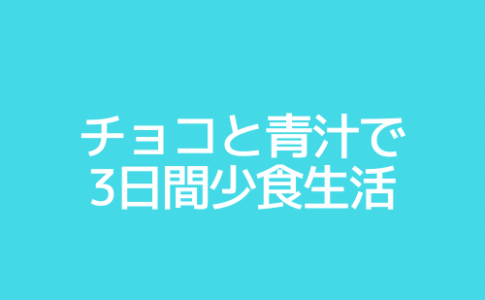
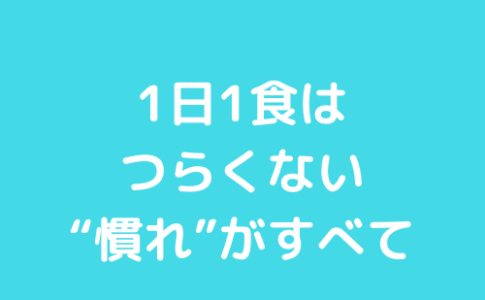


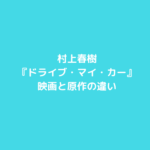
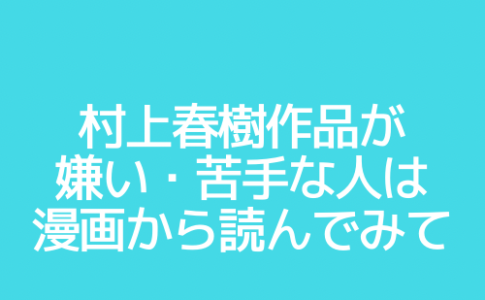

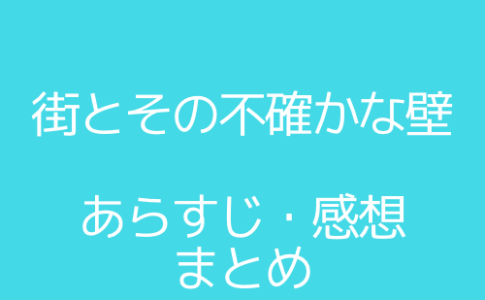

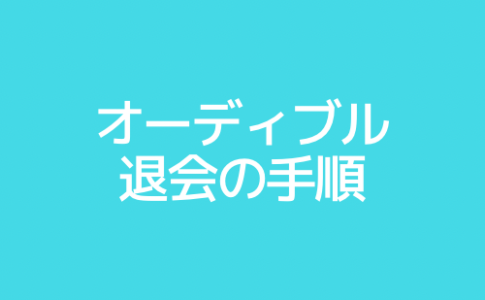
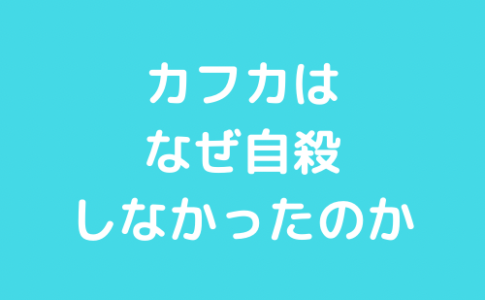

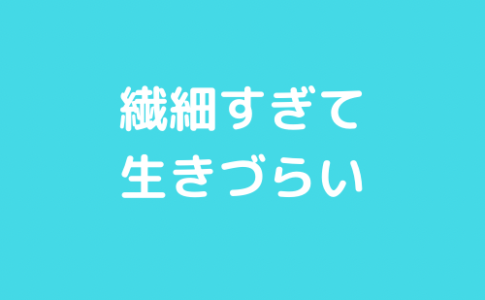
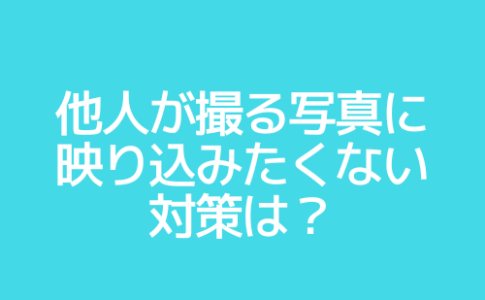
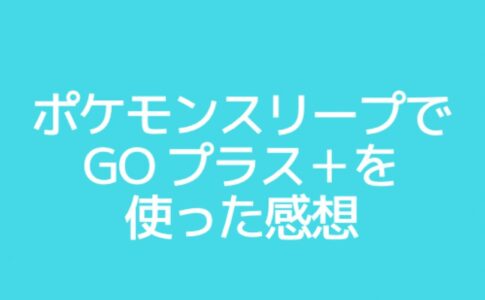
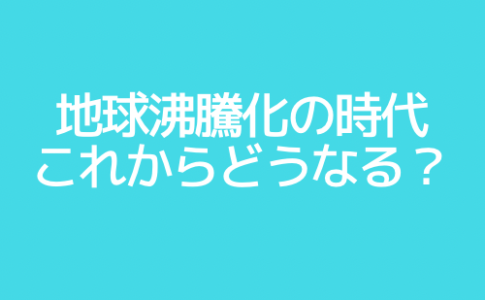
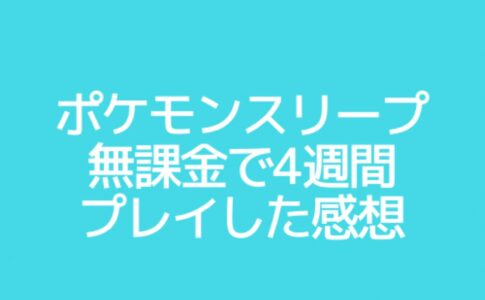
果物だけを1食だけ食べる日→普通の1食の日→果物だけを1食だけ食べる日→普通の1食の日……