社会人ならなかなか避けては通れないものに飲み会ってありますよね。
飲みニケーションなんて言葉もあるくらいに、仕事終わりに一緒にお酒を飲むことでコミュニケーションを深める習慣があります。
まあ、仕事中はおのおのが業務に集中していて、時間をかけて話す場面ってないですからね。
ただ、この飲み会(飲みニケーション)って業務時間以外におこなわれるのは、つらいですよね。
国税庁も”サケビバ”なんていうくだらないことを言っています。
困りましたね。
この飲み会が、会社の経費でおこなわれるならまだいいのですが、割り勘とかだとつらいです。
そもそもそんなにアルコール飲めないし……
時間もお金も出ていく嫌なイベント……
この記事では、飲み会(飲みニケーション)の不要性、それを回避するための方法、対策についてまとめてみました。
もくじ(各リンクから移動できます)
飲み会(飲みニケーション)に対して世間の声(ツイッター)
世間では、やはり飲み会(飲みニケーション)不要派の人も多いようです。
お酒を飲めない人、話すのが苦手な人にとっては、飲み会は苦痛なイベントですよね。
歓送迎会・忘年会などの飲み会(飲みニケーション)を現実的に避ける方法・対策
所属する会社で飲み会がどのくらいの頻度でおこなわれるかわかりませんが、まずはぜんぶ拒否するとなると、少し波風が立ってしまいます。
新人なら新人のために歓迎会だって開かれるでしょうし、行かざるを得ない状況もあるかもしれません(地獄!)。
なので、飲み会(飲みニケーション)開催にあたり、まずは下記からはじめてみましょう。
飲み会に毎回は出ない
とりあえず、まずは2回に1回くらいのペースで様子をみましょう。
絶対に行かない!という姿勢は協調性がないと思われますから、まずは行ったりいかなかったりがおすすめです。
当日や数日前に開催が決まる、ゲリラ的な開催の飲み会なら、「ちょっと別で用事があって……」みたいな理由でじゅうぶん断れます。
普通の人は深くその理由を聞いてきませんが、なかには切り込んで来る人もいるので、そのとき用に嘘予定をつくっておくといいでしょう。
参加する場合、話したくない人の近くに座らない
飲み会で重要なのは、座る席です。
どこに座って誰がとなりの人間なのかによって、居心地の良さが変わってきます。
会社に在籍期間が長くなると、「この人とは話すと疲れるな」と思う人が1人くらいはいるでしょう。
お店に向かいながら、「この人だったら長時間話しても疲れなさそうだな」って思える人を選んで近くにいるのがいいでしょう。
「金欠で」は最強の断り文句
自費での開催の場合、「お金がなくて……」は便利なフレーズです。
どうしても来いよって言われるなら、「おごってくれるなら行きます」というポジションをとれますし。
会社が費用を負担する飲み会の場合は使えませんが。
「少人数なら行く」みたいな条件を出す
すべての飲み会に参加するという姿勢では、飲み会に絶対来るキャラクターになってしまいます。
なので、「私、大人数が苦手なので、4人くらいの少人数であれば行きます」みたいな条件を出しておくのもいいと思います。
すると、大人数の飲み会がある場合、社内の人は「あの人は大人数が苦手だから来ないキャラ」みたいなイメージを持ってくれたりします。
行きたいお店のときだけ行く
飲み会のお店って、当たり外れがありますよね。
自分の好みのお店だったら、つまらなくても食事で楽しめます。
しかし、好みの店じゃなかったら余計につらいです。
なので、飲み会が開催されることがわかったら、まず「どこのお店?」と聞けるといいですね。
そのお店が行きたくない店なら、「●●の店だったら行きたいんだけどねえ」みたいな。
ちょっとわがままと思われてしまうかもしれませんが、自分の好みを伝えちゃいましょう。
お店の変更or「じゃあ、君がお店を選んでくれていいよ」ってなる可能性もなきにしもあらず……ですが。
その場合は、自分の行きたいお店をチョイスできるので、それはそれで良いかもしれません(好みの料理かつ、閉店が早いお店とか)が。
飲み会(飲みニケーション)に出ないでいいように社内で成績を残して立ち場をつくる
飲み会(飲みニケーション)なんて、無駄!古い!絶対に行きたくない!という人も中にはいるでしょう。
そういう人は「社内で仕事の成績を残す」が重要だと感じます。
まずは、しっかりと仕事をこなして、社内で立場をつくることですね。
結局、飲み会(飲みニケーション)って、仕事がうまくいかない人が参加して、普段の成績がよくない業務のマイナス部分を、上司(まわり)のご機嫌をとることで、埋め合わせるみたいな側面があるような気がします。
……みたいな。
極端な言い方になりますが、仕事ができる=飲み会参加の拒否権があるみたいなイメージで良いでしょう。
まあ、会社っていうのは結局、業務をちゃんとやってくれる人を評価する場所です。
仕事さえちゃんとできていれば、飲み会に参加しようが不参加だろうが、関係ないです。
自分は仕事ができないと感じる人はまずは徹底的に無駄をなくして、やるべきことを見極めて仕事をスピーディーにこなし、社内での立場をつくっていきましょう。
そのために、おすすめの本はこちら。
テレ東をやめてフリーで仕事をされている佐久間宣行さんの仕事術をまとめた本です。
この『佐久間宣行のずるい仕事術』は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」の総合グランプリに選ばれるほどの実力派のビジネス書。
まだ仕事に自信がな人、飲み会に参加しなくてもいいほどの圧倒的な仕事術を学びたいなら、この1冊がおすすめ。
この『佐久間宣行のずるい仕事術』は、Amazonオーディブルオーディブルなら通勤時間に気軽に聞けますよ。
ランチやちょっとした休憩等で社内の重要なポジションにいる人とコミュニケーションをはかっておく
夜の飲み会は費用もかかりますし、時間もかかります。
ただ、参加しない場合は、社内の人たちとコミュニケーションをする機会がなくなります。
会社の中で、まわりと協調して業務をこなしていくためには、ある程度コミュニケーションをとっておく必要がありますよね。
そんなときは、夜の飲み会を断りやすくするように、普段からランチの機会を利用して、社内の人とコミュニケーションをはかっておきましょう。
仕事ができる同僚と、あるいは、たまには業務をする上で重要なポジションにいる人と。
80対20の法則(パレートの法則)というものがあります。
たとえば、会社の80%の成果は20%の有能な人が出している、みたいな考え方です。
会社にとって評価されるのはこの20%の有能な人たちです。
なので、この20%のできる人たちと普段からランチの場所などでコミュニケーションをとっておけば、夜の飲み会があったときに不参加であっても、さほど問題にならないと思われます。
飲み会(飲みニケーション)は無駄だし、古いけど、雑談は必要
結局、業務中はみんな自分の仕事で忙しいですし、社員同士でコミュニケーションをはかる機会はないから、飲み会みたいな別の場が必要となるわけですよね。
世間的には飲み会(飲みニケーション)は無駄だし、古いという考え方はわかります(自分もその考え方)。
なので普段から、たとえば、ちょっとした雑談(休憩スペースで数分の会話とか、社内の移動での会話とか、チャットでのやりとりとか)で、ちゃんとコミュニケーションがとれる(そこそこおもしろい)人として、アピールしておくことが大切です。
そうすれば、飲み会参加の問題は回避できるはずです。
さりげない雑談がおもしろい人って、仕事ができる人が多い印象があります。
会社の飲み会が無駄・行きたくないという考え方をどうしても捨てられないなら
会社勤めをしている限り、飲み会問題はつきまとうでしょう。
同僚たちとコミュニケーションをとることは業務を円滑に進めるためには必要ですから。
現代ではまだ飲み会がコミュニケーションをはかるための機会として使われがちです。
もし今あなたが「飲み会なんて無駄!」だと感じるのであれば、会社勤めは性格的におそらく向いていないかもしれませんね。
なので将来的には自宅でフラーランスで働く方が精神的にもストレスがなくいいでしょう。
飲み会を回避できて自宅での仕事となると、1人でPCのみでできる仕事でしょう。
となると、仕事の選択肢はかなり限られてきます。
フリーランスで働くほどのスキルなんてないという場合は、やはりプログラミングを学び始めるのがおすすめ。
経済産業省が2030年にはIT人材が30万人も不足すると発表しています。
飲み会がなく、在宅でフリーで働く未来を手に入れたいなら、まずはプログラミング学習で、IT系の会社に転職。
で、3年ほど実績と実力を積んだら、フリーランスでの生活も現実的になります。
飲み会・お酒の強要もないフリーランス生活にたどりつくための現実的な道筋をあらためて簡単にまとめます。
1.現在の会社での飲み会は上記で紹介した方法で最低限の労力で乗り切る
2.1と並行してプログラミングでの学習
3.プログラミングスキルを武器にIT系企業に転職
4.IT企業で実績を積む(数年)。ここでも飲み会があれば、スキルの情報交換を目的に乗り切る。
5.独立し、飲み会なしのフリーな生活
この方法なら数年後には飲み会なしの生活にたどり着ける可能性が高いでしょう。
会社で会社員をしている限り、飲み会の誘いは確実に来ますし、断る理由を考えたり、丁寧に断ろうとして疲弊していきます。
会社で定年退職するまで「飲み会は無駄……」とか思いながら生きる人生はしんどいです(地獄)。
かなりきついです。
飲み会の心配などせず、仕事のことは純粋に業務のことだけを考える人生を送るなら、将来的にはフリーランスで働くことも視野に入れて生きていくべきです。
そのための1歩目は、プログラミングの学習です。
ただ独学だとかなりの確率で挫折するでしょう。
なので、効率よく手っ取り早く学ぶなら、受講者数No.1のTechAcademy [テックアカデミー]オンラインに特化したプログラミングスクールですし、通う必要がなく、自宅でもWeb制作・プログラミング・アプリ開発を学べます。
エンジニア転職保証コース無料体験でのプログラミングが無理そうだと感じたのなら、『会社での飲み会をうまく回避スキル』を現実的に磨いていくしかないかもしれません。
まとめ
これまでは飲み会に参加自体が、コミニュケーションの手段のメインでした。
しかし、コロナ拡大、テレワークの普及等で飲み会自体が開催できないこともあり、なかにはホッとしている人もいるでしょう。
これからは日々の何気ないチャットのやり取り等で、さりげないユーモアだったり、雑談をできる人が、社内でうまく生きていけるんじゃないかな、という気はします。
仕事中にそんなおもしろいことが言えるようなゆとりなんてないよ、という人は、とりあえず雑談力をあげるための本を読んでみるのもおすすめです。
下記の本は1000以上のレビューがあり、星も4くらいでしたので、わりとためになる本です。
会社勤めの人なら、適度に飲み会との距離をとり、ストレスを最小限にしながら生きていきましょう。
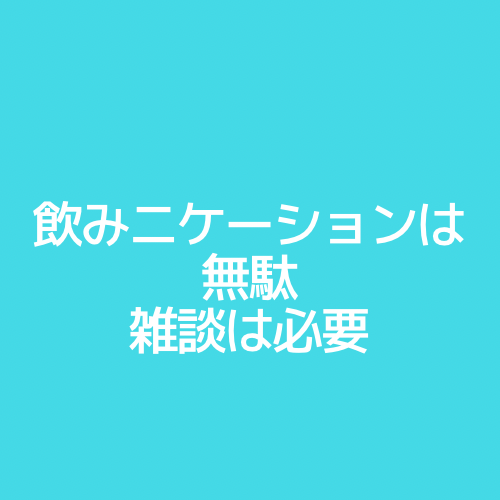
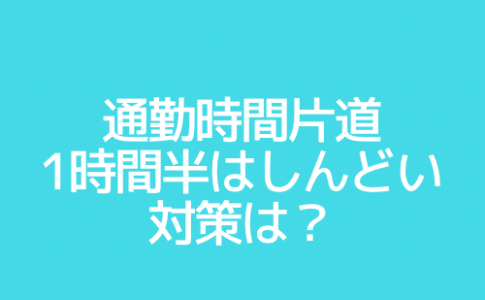
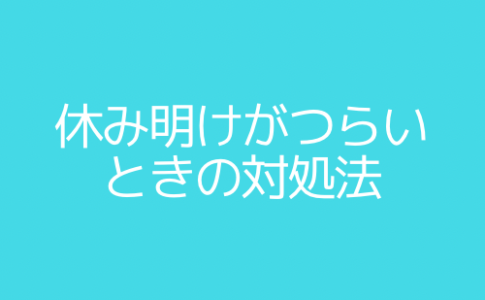
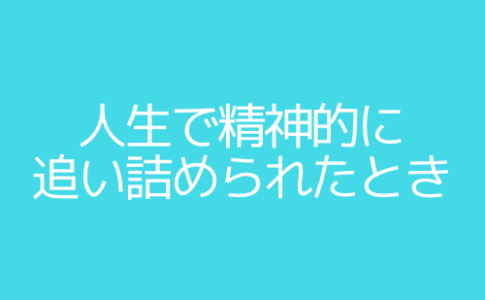
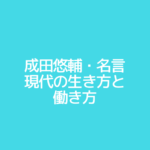
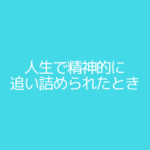
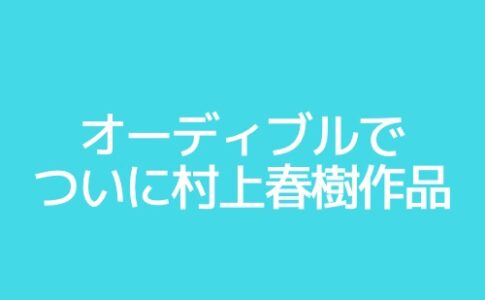
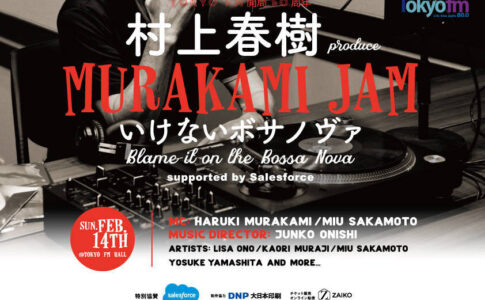
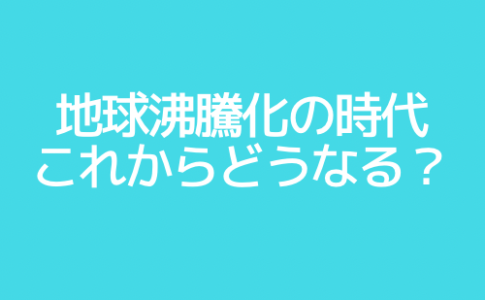

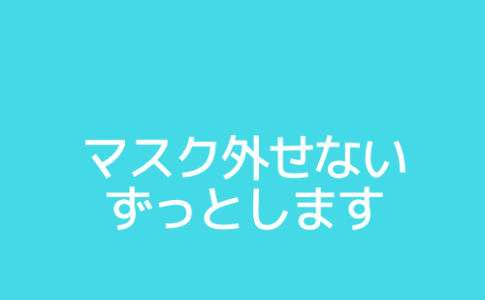
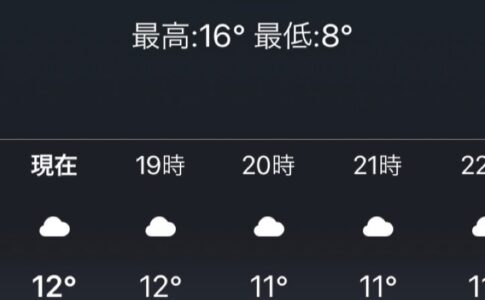
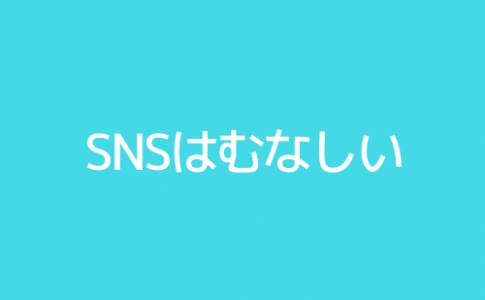

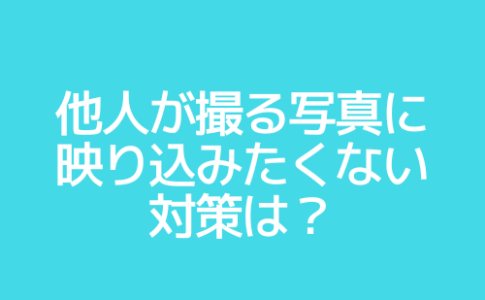
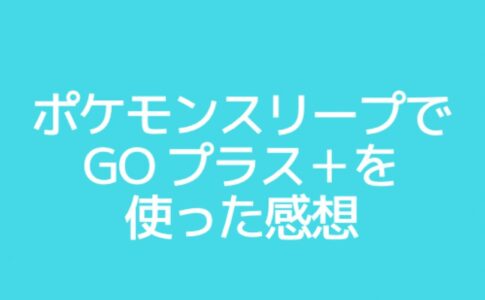
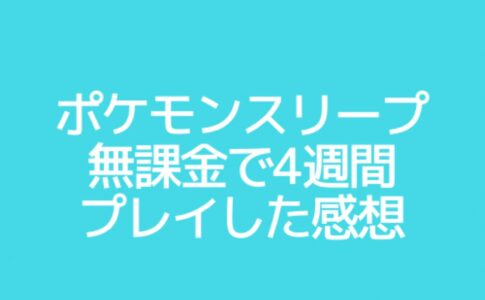
【仕事ができなくて、飲み会に参加しない場合】
→上司の声(or まわり)「あいつ、仕事もできないし、飲み会でコミュニケーションをとろうともしないし、最悪だわ」
【仕事ができて、飲み会に参加しない場合】
→上司の声(or まわり)「あいつ、仕事はできるけど、飲み会にもこないな。まあ、そういう人もいるよな」